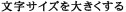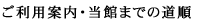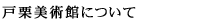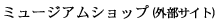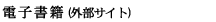2024年3月
予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
日月火水木金土
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
312024年4月
予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
日月火水木金土
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829302024年5月
予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
日月火水木金土
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930312024年6月
予定は変更となる場合がございます。予めご了承ください。
日月火水木金土
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
302022年8月13日
ラウンジトーク「古伊万里入門」(予約不要/先着20名)
2022年8月27日
ラウンジトーク「『古伊万里西方見聞録展』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2022年9月28日
ラウンジトーク「『古伊万里西方見聞録展』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2022年10月14日
メモリアルデーのため入館料無料
2022年10月24日
ラウンジ&ギャラリートーク「戸栗美術館収蔵のマイセン磁器-伊万里焼との影響関係を中心に-」(要予約/先着)
2022年11月7日
展示替えに伴う休館
2022年11月8日
展示替えに伴う休館
2022年11月9日
展示替えに伴う休館
2022年11月10日
展示替えに伴う休館
2022年11月11日
展示替えに伴う休館
2022年11月12日
展示替えに伴う休館
2022年11月13日
展示替えに伴う休館
2022年11月14日
展示替えに伴う休館
2022年11月15日
展示替えに伴う休館
2022年11月16日
展示替えに伴う休館
2022年11月17日
展示替えに伴う休館
2022年11月18日
展示替えに伴う休館
2022年11月19日
展示替えに伴う休館
2022年11月20日
展示替えに伴う休館
2022年11月21日
『開館35周年記念特別展 戸栗美術館 名品展Ⅱ-中国陶磁-』開催初日
2022年11月26日
ラウンジトーク「『戸栗美術館名品展Ⅱ-中国陶磁-』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2022年12月5日
ラウンジ&ギャラリートーク「戸栗コレクションの中国陶磁」(要予約/先着)
2022年12月14日
ラウンジトーク「『戸栗美術館名品展Ⅱ-中国陶磁-』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2022年12月29日
『開館35周年記念特別展 戸栗美術館名品展Ⅱ-中国陶磁-』最終日
2022年12月30日
展示替えに伴う休館
2022年12月31日
展示替えに伴う休館
2023年1月1日
展示替えに伴う休館
2023年1月2日
展示替えに伴う休館
2023年1月3日
展示替えに伴う休館
2023年1月4日
展示替えに伴う休館
2023年1月5日
展示替えに伴う休館
2023年1月6日
展示替えに伴う休館
2023年1月7日
展示替えに伴う休館
2023年1月8日
展示替えに伴う休館
2023年1月9日
展示替えに伴う休館
2023年1月10日
展示替えに伴う休館
2023年1月11日
展示替えに伴う休館
2023年1月12日
展示替えに伴う休館
2023年1月13日
展示替えに伴う休館
2023年1月14日
展示替えに伴う休館
2023年1月15日
『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』初日
2023年2月18日
ラウンジトーク「『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2023年2月27日
ラウンジ&ギャラリートーク「戸栗コレクションの朝鮮陶磁」(要予約/先着)
2023年3月8日
ラウンジトーク「『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』の見どころ」(予約不要/先着20名)
2023年3月26日
『開館35周年記念特別展 初期伊万里・朝鮮陶磁』最終日
2023年3月27日
展示替えに伴う休館
2023年3月28日
展示替えに伴う休館
2023年3月29日
展示替えに伴う休館
2023年3月30日
展示替えに伴う休館
2023年3月31日
展示替えに伴う休館
2023年4月1日
展示替えに伴う休館
2023年4月2日
展示替えに伴う休館
2023年4月3日
展示替えに伴う休館
2023年4月4日
展示替えに伴う休館
2023年4月5日
展示替えに伴う休館
2023年4月6日
展示替えに伴う休館
2023年4月7日
展示替えに伴う休館
2023年4月8日
「『柿右衛門』の五色―古伊万里からマイセン、近現代まで―」初日
2023年4月15日
展示解説『「柿右衛門」の五色―古伊万里からマイセン、近現代まで―』の見どころ(予約不要)
2023年5月3日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(要予約/先着)
2023年5月4日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(要予約/先着)
2023年5月5日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(要予約/先着)
2023年5月15日
ラウンジ&ギャラリートーク「彩色にみる古伊万里・マイセン・近現代の『柿右衛門』」(要予約/先着)
2023年5月28日
特別講演会 15代酒井田柿右衛門氏による「柿右衛門の世界」
2023年6月10日
展示解説『「柿右衛門」の五色―古伊万里からマイセン、近現代まで―』の見どころ(予約不要)
2023年6月25日
『「柿右衛門」の五色―古伊万里からマイセン、近現代まで―』最終日
2023年6月26日
展示替えに伴う休館
2023年6月27日
展示替えに伴う休館
2023年6月28日
展示替えに伴う休館
2023年6月29日
展示替えに伴う休館
2023年6月30日
展示替えに伴う休館
2023年7月1日
展示替えに伴う休館
2023年7月2日
展示替えに伴う休館
2023年7月3日
展示替えに伴う休館
2023年7月4日
展示替えに伴う休館
2023年7月5日
展示替えに伴う休館
2023年7月6日
展示替えに伴う休館
2023年7月7日
『古伊万里の「あを」―染付・瑠璃・青磁―』初日
2023年7月17日
展示解説『古伊万里の「あを」―染付・瑠璃・青磁―』の見どころ(予約不要)
2023年7月24日
ラウンジ&ギャラリートーク「『Japan Blue』と古伊万里の青」(要予約/先着)
2023年8月12日
展示解説「古伊万里入門解説」(予約不要)
2023年9月9日
展示解説『古伊万里の「あを」―染付・瑠璃・青磁―』の見どころ(予約不要)
2023年9月24日
『古伊万里の「あを」―染付・瑠璃・青磁―』最終日
2023年9月25日
展示替えに伴う休館
2023年9月26日
展示替えに伴う休館
2023年9月27日
展示替えに伴う休館
2023年9月28日
展示替えに伴う休館
2023年9月29日
展示替えに伴う休館
2023年9月30日
展示替えに伴う休館
2023年10月1日
展示替えに伴う休館
2023年10月2日
展示替えに伴う休館
2023年10月3日
展示替えに伴う休館
2023年10月4日
展示替えに伴う休館
2023年10月5日
展示替えに伴う休館
2023年10月6日
『伊万里・鍋島の凹凸文様』初日
2023年10月14日
メモリアルデーのため入館料無料
2023年10月21日
展示解説『伊万里・鍋島の凹凸文様』の見どころ(予約不要)
2023年11月27日
ラウンジ&ギャラリートーク「伊万里・鍋島の陰刻・陽刻技法とその変遷」(要予約/先着)
2023年12月9日
展示解説『伊万里・鍋島の凹凸文様』の見どころ(予約不要)
2023年12月21日
『伊万里・鍋島の凹凸文様』最終日
2023年12月22日
展示替えに伴う休館
2023年12月23日
展示替えに伴う休館
2023年12月24日
展示替えに伴う休館
2023年12月25日
展示替えに伴う休館
2023年12月26日
展示替えに伴う休館
2023年12月27日
展示替えに伴う休館
2023年12月28日
展示替えに伴う休館
2023年12月29日
展示替えに伴う休館
2023年12月30日
展示替えに伴う休館
2023年12月31日
展示替えに伴う休館
2024年1月1日
展示替えに伴う休館
2024年1月2日
展示替えに伴う休館
2024年1月3日
展示替えに伴う休館
2024年1月4日
展示替えに伴う休館
2024年1月5日
展示替えに伴う休館
2024年1月6日
展示替えに伴う休館
2024年1月7日
『花鳥風月―古伊万里の文様』初日
『花鳥風月―古伊万里の文様―』初日
2024年1月20日
展示解説「『花鳥風月―古伊万里の文様―』の見どころ」(予約不要)
2024年2月24日
展示解説「『花鳥風月―古伊万里の文様―』の見どころ」(予約不要)
2024年3月11日
ラウンジ&ギャラリートーク「古伊万里の文様―中国文化受容のその先へ―」(要予約/先着)
2024年3月21日
『花鳥風月―古伊万里の文様』最終日
『花鳥風月―古伊万里の文様―』最終日
2024年3月22日
展示替えに伴う休館
2024年3月23日
展示替えに伴う休館
2024年3月24日
展示替えに伴う休館
2024年3月25日
展示替えに伴う休館
2024年3月26日
展示替えに伴う休館
2024年3月27日
展示替えに伴う休館
2024年3月28日
展示替えに伴う休館
2024年3月29日
展示替えに伴う休館
2024年3月30日
展示替えに伴う休館
2024年3月31日
展示替えに伴う休館
2024年4月1日
展示替えに伴う休館
2024年4月2日
展示替えに伴う休館
2024年4月3日
展示替えに伴う休館
2024年4月4日
展示替えに伴う休館
2024年4月5日
展示替えに伴う休館
2024年4月6日
展示替えに伴う休館
2024年4月7日
展示替えに伴う休館
2024年4月8日
展示替えに伴う休館
2024年4月9日
展示替えに伴う休館
2024年4月10日
展示替えに伴う休館
2024年4月11日
展示替えに伴う休館
2024年4月12日
展示替えに伴う休館
2024年4月13日
展示替えに伴う休館
2024年4月14日
展示替えに伴う休館
2024年4月15日
展示替えに伴う休館
2024年4月16日
展示替えに伴う休館
2024年4月17日
『鍋島と金襴手―繰り返しの美―展』初日
2024年5月1日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(10時30分~13時、要予約/先着)
2024年5月2日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(10時30分~13時、要予約/先着)
2024年5月3日
アート&イート戸栗美術館×シェ松尾(10時30分~13時、要予約/先着)
2024年5月18日
展示解説「『鍋島と金襴手―繰り返しの美―展』の見どころ」(14時~、予約不要)
2024年5月27日
ラウンジ&ギャラリートーク「繰り返すデザイン―鍋島焼と金襴手様式の伊万里焼を紐解く4つのアプローチ―」(要予約/先着)
2024年6月15日
展示解説「『鍋島と金襴手―繰り返しの美―展』の見どころ」(14時~、予約不要)
2024年7月1日
展示替えに伴う休館
2024年7月2日
展示替えに伴う休館
2024年7月3日
展示替えに伴う休館
2024年7月4日
展示替えに伴う休館
2024年7月5日
展示替えに伴う休館
2024年7月6日
展示替えに伴う休館
2024年7月7日
展示替えに伴う休館
2024年7月8日
展示替えに伴う休館
2024年7月9日
展示替えに伴う休館
2024年7月10日
展示替えに伴う休館
2024年7月11日
『古伊万里から見る江戸の食展』初日
2024年7月15日
展示解説「『古伊万里から見る江戸の食展』の見どころ」(14時~、予約不要)
『古伊万里から見る江戸の食展』
『鍋島と金襴手―繰り返しの美―展』
休館日
夜間開館
イベント

.jpg)